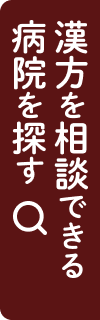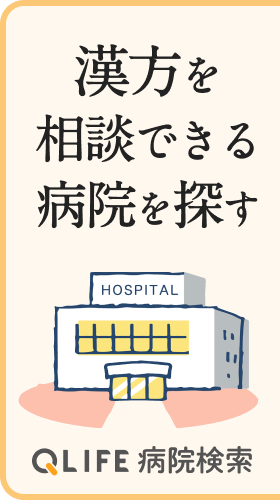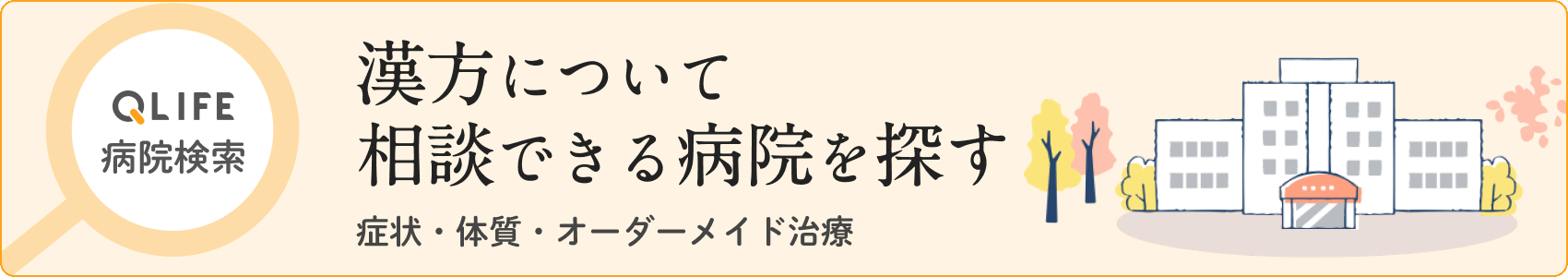コラム:人によって異なる漢方薬の作用

漢方薬がもたらす効果について、西洋薬と比較しながらもう少し詳しく解説します。
実は漢方薬には「服用した人と呼応(反応)した時だけ薬剤の作用をする」という特徴があり、それが効果をもたらすうえでの重要なポイントとなります。
漢方薬は、植物の根、果実、種子、葉、鉱物などを加工した生薬を組み合わせて作られており、単一の成分が大量に含まれているわけではありません。西洋医学の薬のほとんどが単一の成分でできていますから、ここが西洋薬と漢方薬との大きな違いです。漢方薬は、1つ1つの成分の量は少ないのですが、いくつかの成分が集まり、その相互作用で効果を現すこともあります。
薬剤は、「応答を引き出す」という、体への働き方を持っています。「応答」とはいわば、体を動かす「システム」に変調を来たしたときにそれを直そうとする体の防衛反応です。
西洋医学の薬剤は服用すればどんな人にも同じ効果を発揮します。たとえば血圧を下げる作用のある降圧剤は、血圧の高くない人にも降圧効果を示すので、人によっては服用することで危険な状態を引き起こすことがあります。これは、西洋医学の薬とシステムが、1対1の応答をするからです。一方、漢方薬は、複数のシステムに複雑に働きかけます。服用した人がその漢方薬に呼応した場合、有効成分が一斉に、あるいは時間差で働きかけることで、特定の応答が引き出されて体のシステムが正常化され、症状を改善しています。応答がなければ、漢方薬は薬剤の作用を示しません。さらに、そもそも服用してもその薬に呼応しない人もいます。呼応しない場合は、満足できる効果が得られません。これが、同じ漢方薬を服用しても、人によって得られる作用が異なることの理由です。
たとえば、こむら返りによく使われる芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)という漢方薬がありますが、服用した場合、こむら返りを起こした人だけが効果を得られ、起こしていない人にはまったく変化をもたらさないのです。芍薬甘草湯は、こむら返りのときに起こる筋肉の痙攣を緩める「応答を引き出す」ため、過剰に筋肉が緩んでしまうこともありません。そのため、予防として用いることもできるのです。
漢方薬は、このように、システムを正常化する応答を引き出す薬剤です。
それは、言い換えると、病気を治す自分自身が持つ力を引き出すということでもあります。薬の力によって病気を治すのではなく、自分自身が持っている力を引き出す役割を漢方薬が担ってくれることで、自分の力で病気を克服するのが、漢方薬の効果なのです。