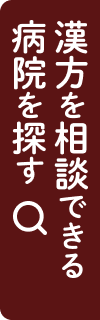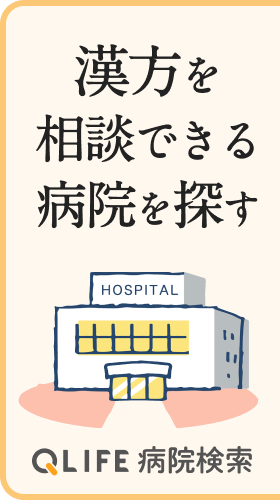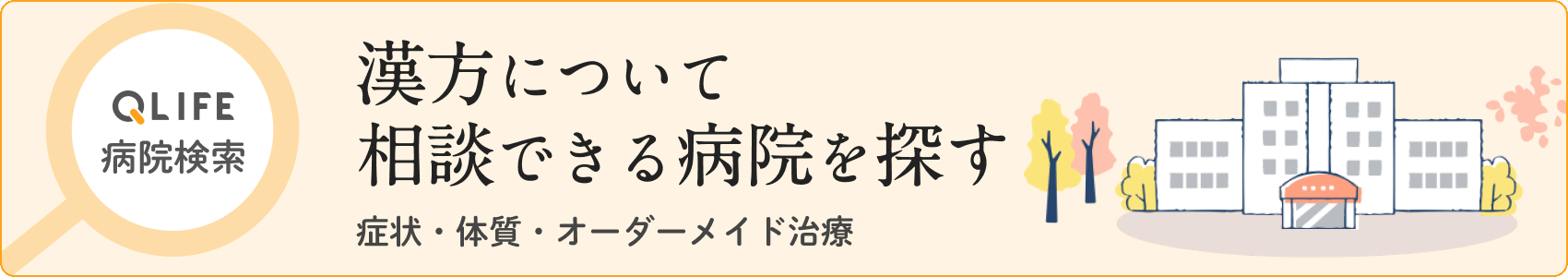漢方薬の飲み合わせや禁忌は? 西洋薬と併用するケースや複数の漢方薬を服用するケースでの注意点も紹介
薬剤には併用してはいけない組み合わせ(禁忌)があります。このことは、西洋薬だけでなく漢方薬にも当てはまり、服用する際は注意が必要なこともあります。ここでは、漢方薬と西洋薬、複数の漢方薬の併用、水以外の飲み物や食べ物との飲み合わせについて、注意すべきポイントを解説します。
漢方薬の飲み合わせで気をつけること
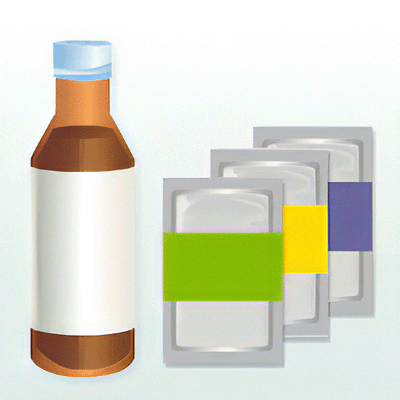
漢方薬は、2つ以上の生薬(植物や動物、鉱物などの薬効となる部分)を組み合わせて作られていますので、漢方薬はひとつの薬剤の中にいくつもの有効成分が含まれます。そのため、複数の漢方薬を同時に服用すると、効果が強く出過ぎてしまったり、あるいは逆に効果が弱まってしまったりするという「飲み合わせ」の問題が出てきます。
医療機関で漢方薬を出してもらう場合は、医師や薬剤師が飲み合わせの問題がないかどうかを確かめてから処方・調剤します。
自分で市販の漢方薬を買うときは、飲み合わせの確認ができない場合が多いので、自分の判断で市販の漢方薬を同時に複数飲むことは避けましょう。また、心配なことや疑問に思うことがあったら、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。
いずれの場合もおくすり手帳などで他に飲んでいる薬のことを知らせて、確認してもらうと安心です。
西洋薬と併用するケース
漢方薬と西洋薬を併用することはよくあります。西洋薬の効果をサポートしたり、副作用を軽減したり、西洋薬では対応できない症状を改善したりすることがあるからです。
一方で、漢方薬と西洋薬を併用するケースとして、絶対に併用してはいけない(禁忌)の組み合わせがあります。肝炎やがんなどの治療に使われるインターフェロン製剤は、合併症として間質性肺炎(肺の間質といわれる部分に炎症が起きる病気)を起こすことがあります。小柴胡湯(しょうさいことう)を併用することでその頻度が増大するという報告があり、1994年から国が両者の併用を禁止しています。
インターフェロン製剤は注射薬であり、使われる病気も肝炎やがんなどに限定されていますので、一般の方がうっかり飲んでしまうということは考えにくいですが、医療機関で治療を受けるときには、飲んでいる漢方薬(市販薬も含む)を医師や薬剤師に知らせるようにしましょう。
他にも、禁止されてはいませんが、慎重に使うべき組み合わせとして、下記のようなものがあります。
甘草による副作用である偽アルドステロン症(高血圧、低カリウム血症、むくみ、不整脈、脱力など)が起きやすくなる
●麻黄(まおう)の入った漢方薬と喘息薬、抗うつ剤、甲状腺の薬、かぜ薬など
交感神経を強く刺激し、不眠、興奮、頻脈、動悸、発汗、脱力などが起きやすくなる
●地黄(じおう)、麻黄(まおう)、当帰(とうき)、川芎(せんきゅう)、呉茱萸(ごしゅゆ)の入った漢方薬と消炎鎮痛剤、抗生物質
胃腸の機能低下が起こる可能性がある
●タンニンが入った漢方薬と鉄剤、酵素剤
タンニンが鉄剤や酵素剤の効果を低下させる可能性がある
ここにあげた漢方薬や西洋薬には多くの種類があり、一般の方には判断が難しいことがあります。おくすり手帳などを利用して飲んでいる漢方薬を医師・薬剤師に伝えるようにしましょう。
複数の漢方薬を服用するケース
漢方薬はいくつかの生薬を組み合わせて作られていますので、複数の漢方薬を飲むと生薬が重複してしまう場合があります。
特に重複に気をつけたい生薬は「甘草」「麻黄」「附子(ぶし)」「大黄(だいおう)」です。これらはひとつの漢方薬に含まれる量であれば問題にはなりにくいですが、複数の漢方薬を飲んで重複してしまった場合、量が多くなるので副作用が出やすくなります。
多くの漢方薬で使われている生薬で、重複するリスクが高いので注意しましょう。甘草を多量に服用すると、偽アルドステロン症(高血圧、低カリウム血症、むくみ、不整脈、脱力など)が起きやすくなります。
●麻黄
交感神経を強く刺激し、不眠、興奮、頻脈、動悸、発汗、脱力などが起きやすくなります。
●附子
動悸や舌のしびれが現れることがあります。
●大黄
下痢をすることがあります。
漢方薬を複数飲むときは、それぞれの漢方薬にどんな生薬が入っているのかを確認するようにしましょう。薬剤師に確認をお願いすることもできます。
水以外の飲み物・食べ物との飲み合わせ
西洋薬では飲み物・食べ物との飲み合わせに注意しなければならないケースがありますが、漢方薬も同じように飲み合わせがあるのでしょうか。
そもそも、漢方薬は空腹時(食前または食間)に飲むことが基本です。それは消化管内に食物がある状態で漢方薬を服用すると効果が弱まる(食物繊維が漢方薬の成分を吸着する)からです。そのため「何々を食べてはいけない」というよりも、服用タイミングに注意する必要があります。
飲み物については、漢方薬は水や白湯で飲むのが基本です。オブラートや服薬補助ゼリーに包み込むと飲みやすくなります。お茶やコーヒー、牛乳、ジュースなどは薬の働きに影響を与える可能性があるため、あまりおすすめできません。どうしても漢方薬の苦みを和らげたい場合は、コーヒー、ココア、抹茶などと混ぜて飲んでみてください。
代表的な漢方薬の飲み合わせの注意点
ここでは、よく使われる漢方薬について、飲み合わせに気をつけたいものをご紹介します。ここに記載がないものもありますので、漢方薬を処方されたときや購入するときには、いま飲んでいる西洋薬や市販薬を含めて医師や薬剤師に伝えて、確認をお願いしましょう。
葛根湯の飲み合わせ
葛根湯(かっこんとう)は初期のかぜや炎症性疾患、肩こりなどに使われることの多い処方です。配合生薬のうち、併用時に特に注意が必要なのは麻黄と甘草です。下記の薬剤との飲み合わせに特に注意しましょう。
市販のかぜ薬、鼻炎薬、咳止め薬など
●麻黄を多く含む漢方薬
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、麻黄湯(まおうとう)、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)など
●交感神経を刺激する成分(テオフィリン、ジプロフィリンなど)
咳止め薬など
●グリチルリチン酸(甘草の成分)
かぜ薬、鼻炎薬、トローチなど
●甘草を多く含む漢方薬
芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、抑肝散(よくかんさん)など
漢方薬については通常は同時に処方されることはありませんが、自己判断による市販の漢方薬との併用は避けましょう。
麻黄湯の飲み合わせ
かぜのひきはじめや初期のインフルエンザに使われることの多い麻黄湯に配合されている生薬のうち、飲み合わせに気をつけたいのは同じく麻黄と甘草です。下記の薬剤との飲み合わせに特に注意しましょう。
市販のかぜ薬、鼻炎薬、咳止め薬など
●麻黄を多く含む漢方薬
葛根湯(かっこんとう)、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)など
●交感神経を刺激する成分(テオフィリン、ジプロフィリンなど)
咳止め薬など
●グリチルリチン酸(甘草の成分)
かぜ薬、鼻炎薬、トローチなど
●甘草
芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、抑肝散(よくかんさん)など
八味地黄丸の飲み合わせ
八味地黄丸に配合されている生薬のうち、飲み合わせに気をつけたい生薬は附子です。特に下記の薬剤との飲み合わせに注意しましょう。
強心剤(どうき、息切れ、気つけ薬)、鎮痛薬など
●附子を多く含む漢方薬
牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)、大防風湯(だいぼうふうとう)、麻黄附子細辛湯など
大黄甘草湯の飲み合わせ
大黄甘草湯に配合されている生薬は、その名の通り大黄と甘草です。大黄は瀉下作用(下痢を起こす作用)を持ち、便秘薬(下剤)として使われます。大黄の効果には個人差がありますが、服用量が多くなると下痢をする可能性が高まり、だんだん効きが悪くなってくる(依存性がある)ことが知られています。
いずれも飲み合わせに気をつけたい生薬です。特に下記の薬剤との飲み合わせに注意しましょう。
下剤など
●大黄を多く含む漢方薬
桃核承気湯(とうかくじょうきとう)や麻子仁丸(ましにんがん)など
●ビサコジルやピコスルファートナトリウム、センナ
刺激性便秘薬
●グリチルリチン酸(甘草の成分)
かぜ薬、鼻炎薬、トローチなど
●甘草を多く含む漢方薬
芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、抑肝散(よくかんさん)など
●鉄剤や酵素剤
大黄に含まれるタンニンによって効果が低下する可能性がある
- 参考
-
- 北村正樹.漢方薬の副作用・相互作用.耳展 1997; 40:109-112.