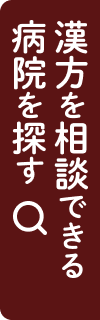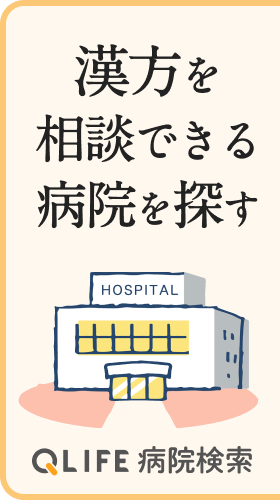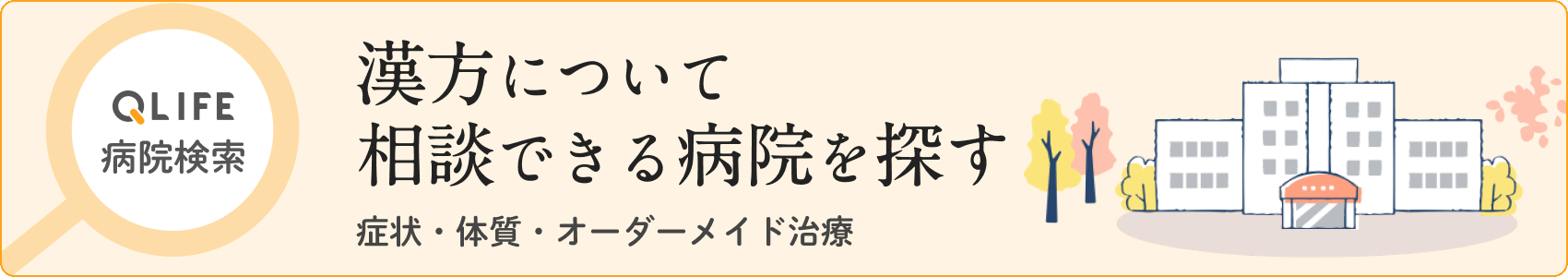煎じ薬のメリットと作り方、服薬継続のコツを紹介
漢方薬には、煎じ薬(煎剤)とエキス剤があります。煎じ薬は漢方薬を構成する数種類の生薬を水から煮出したものです。ここでは、煎じ薬とエキス剤の違いやメリット、具体的な煎じ方や服薬継続の工夫、よくある質問について解説します。
煎じ薬とは
煎じ薬とは、処方ごとに調合された生薬を水から数十分煮出し、成分を抽出させたものを飲むという、伝統的な漢方薬の服用方法です。
一般的に漢方薬は細かい粒状(顆粒)であることが多く、これはエキス剤と呼ばれます。エキス剤は、煎じ薬を濃縮、乾燥、粉末化したものです。
コーヒーに例えると、エキス剤はインスタントコーヒーで、煎じ薬はコーヒー豆をフィルターで漉して淹れるドリップコーヒーのようなものです。

煎じ薬のメリット
煎じ薬のメリットは、その人に合った量の生薬を処方でき、有効成分を余すことなく摂取できることです。
一般的なエキス剤は漢方薬の種類によって生薬の配合が決まっていますが、煎じ薬なら症状や病気の度合い、体質や体力、抵抗力など、その人の状態を表す「証(しょう)」などに応じて、配合する生薬の量を加減することができます。
また、煎じ薬は液状であるため消化吸収がよく、水に溶けにくい成分(にごりの部分)も服用できるため、生薬の有効成分をすべて摂取することができます。煎じている最中に生じるアロマ(精油成分)効果も期待できます。エキス剤では顆粒状に加工するために添加物が使われますが、煎じ薬には添加物が入らないこともメリットです。
しかし、煮出す手間がかかる、服用するまでに時間を要するなどのデメリットがあります。また、生薬は天候や産地などでばらつきが生じやすいため、処方した病院や薬局等によって品質に差が出やすいという問題もあります。
一方、エキス剤は煎じ薬で挙げられるデメリットが少なく、携帯しやすく飲みやすいといえます。小児や高齢者など、用量を考慮すべき場合に少量ずつ使えるメリットもあります。また、品質のばらつきや変質といった問題も抑えられるようになっています。
生薬の品質の問題を除けば、煎じ薬とエキス剤のどちらも漢方薬としての効能に違いはありません。処方される医療機関によっては、煎じ薬とエキス剤を選べます。好みやその時の症状などに応じて、漢方薬のさまざまな剤形を試してみるのもよいでしょう。
煎じ薬の作り方
自宅で煎じ薬を作る際には、土鍋もしくはステンレスやホーロー、耐熱性ガラス等のやかん・鍋を用意しましょう。鉄や銅でできた容器は生薬の成分を変質させてしまうことがあるので避けましょう。また、タイマーを用意しておくと便利です。
- 煎じる容器の中に1日分の煎じ薬と水(水道水でOK)を600mL入れる
- とろ火(10分くらいで沸騰するような火加減)で約40~50分間、約300mL(当初の量の半分)になるまで煎じる
- 熱いうちに火からおろして、茶こしやガーゼなどでかすを漉す
- 煎じ薬は服用回数に応じて等分に分ける(例:1日2回なら半分ずつ)
- 冷蔵庫に保管して24時間以内に飲み切る。出血などがない病気の場合は、一回分の煎薬を再加熱して服用する
煎じている最中はふきこぼれないように、ふたをずらすか、外しておくとよいでしょう。また、熱いうちにかすを漉すことが大切です。冷めてからだと、生薬の成分がかすに吸収されてしまうことがあります。数日分をまとめて煎じるといたむ場合があるので、なるべく毎日1日分ずつ煎じるようにしてください。
煎じ薬の服薬継続の工夫① 煎じ器
煎じ薬は、毎日1時間ほど手間をかけて煎じる必要があります。漢方薬は処方された通りに毎日飲み続けることが大切ですが、煎じる時間や手間をかけられなくて服用できないという場合があり得ます。
煎じることができない日が増えてきた、煎じるのが面倒になってきた、というようなときには、漢方煎じ器を導入してみてはいかがでしょうか。漢方煎じ器はボタンひとつで自動的に煎じてくれる電動ポットで、つきっきりでなくても安心して煎じ薬を作ることができます。
煎じ薬の服薬継続の工夫② 薬局に依頼する
自分で煎じ薬を作るのがむずかしい場合は、煎じを代行してくれるサービスを行っている薬局に依頼するという方法があります。薬局で漢方薬を煎じて、レトルトパックのような長期保存できる袋に詰めてくれます。これなら旅行先などにも持っていくことができ、便利です。
煎じ代行サービスを行っている薬局の中には、遠方でもネット上で依頼できるサービスがあります。ただし、通常は煎じ代行として費用が別途かかりますので、事前に確認するようにしましょう。
よくある質問
煎じ薬に関するよくある質問についてまとめました。
煎じ薬を水筒に入れて持ち歩いてもいい?
煎じ薬は通常、冷蔵で保存するものですので、煎じ薬を水筒に入れて持ち歩く場合は、最大で1日分までにしましょう。できれば保温性の高い水筒を使うことをおすすめします。また、水筒に直接口をつけて飲むと雑菌が繁殖してしまう可能性があるので、コップに注いで飲むようにしてください。
2日以上の旅行や出張などがある場合は、そのときだけ煎じ薬ではなくエキス剤に切り替える方法があります。また、薬局の煎じ代行サービスを利用して、パックに詰めた煎じ薬を持ち歩く方法もあります。
煎じ薬の出がらしをもう一度煎じてもいい?
二煎目を一煎目と合わせて1日分とする飲み方もあり、特に中国などで行われています。漢方薬の内容と病状によって異なりますので、処方医に尋ねるのがよいでしょう。
煎じ薬は服用後どれくらいで効果が出る?
煎じ薬だから効き目が出るのが早い、エキス剤だから遅いということはありません。効果が実感できるタイミングは、処方された漢方薬と症状・体質により異なります。急性疾患(風邪など)向けの漢方薬は飲んですぐに効果が実感できることが多いですし、慢性疾患や体質改善のための漢方薬なら数か月かかる場合もあります。
煎じ薬は保険適用される?
漢方薬はエキス剤でも煎じ薬でも基本的に健康保険を使うことができます。ただし、保険適用が認められていない特殊な生薬を用いる場合は自由診療(全額自己負担)になります。また、医療機関によっては自由診療しか行っていないところもあります。受診する際には健康保険が使えるかどうかを事前に確認しておくと安心です。
あきば伝統医学クリニック院長