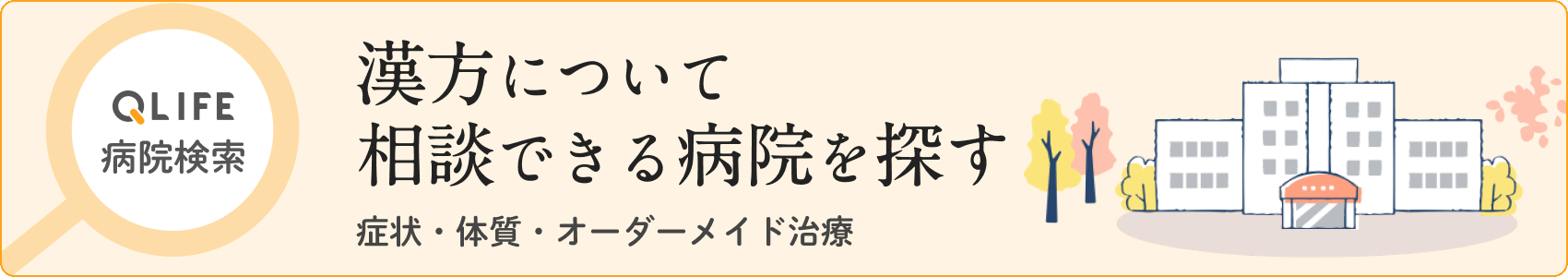漢方薬は「非科学的」なもの? 漢方薬を活用するうえで知っておきたい「エビデンス」とは
日本の医療・ヘルスケアにおいて漢方薬は身近な存在です。しかし、漢方薬の捉え方は人それぞれで、全幅の信頼を置く人がいれば、疑わしいと考える人もいます。私たちは漢方薬をどのように捉え、どう活用していけばよいのでしょうか。
今回は、漢方・統合医療の社会薬学を専門とする日本薬科大学の副学長/教授の新井一郎先生に、漢方に興味がある一般市民向けに「漢方を活用するうえで知っておいてほしいこと」を伺いました。
漢方薬は、近代医学以前より存在する「非科学的」なルーツを持つ医薬品

日本薬科大学 副学長/教授 新井一郎先生
「漢方薬は非科学的だ」と言う人がいます。確かに漢方薬は科学的ではない側面があります。なぜなら、いわゆる科学である近代医学が発展したのはほんの数百年前のこと。漢方薬には数千年の歴史がありますから、科学でないのはむしろ当然だといえます。漢方を非科学的だと批判するのは筋違いでしょう。
人間は数千年にわたり「その辺に生えてる草を食べたら、なぜか症状が改善した」という経験を積み重ねてきました。いわば人体実験のようなことを繰り返して、薬と毒の知見を得てきたのです。それが現代にまで伝わる漢方医学の基礎となっています。
西洋薬は科学的に分析され、有効成分を均一に含有しており、有効性と安全性が担保されています。一方、漢方薬は非科学的なルーツを持ち、さまざまな成分の混合物で、常に同じ成分量を含むとは限らないものです。ただ、もちろん国の承認を受けて製造販売がなされている医薬品ですので、いわゆる健康食品を含む食品とは一線を画すものです。
しかしながら、そもそも漢方薬も西洋薬も、いずれも人体から見れば体外の物・異物です。西洋薬と漢方薬とではルーツもエビデンス確立の方法も異なりますが、人間の体内にない成分を取り入れることによって、身体に何らかの影響を与え、症状が改善する(もしくは有害事象が起こる)という点は同じです。
「病気そのものを治す」のが西洋薬、「症状を治す」のが漢方薬
漢方薬は科学が発展するずっと前からありました。西洋医学的な病気が同定される前からあったので、病名ではなく自覚症状(痛い、かゆい等)に対応しています。
そのため、漢方薬の説明書(添付文書)の効能・効果の欄には、まず自覚症状が書いてあって、その後に西洋医学的な病名が記載されています。漢方薬は症状を治すのがメインであって、病気そのものを治すという概念ではありません。添付文書の病名は補足として記載があるにすぎません。
漢方薬は自覚症状に基づく薬ですから、一般の方にも分かりやすいのが利点です。しかし、それを「添付文書にある症状すべてに必ず効く」と拡大解釈してはいけません。
漢方薬は、漢方薬が得意とする領域で使うべき
実は私は、西洋薬で治せるものを、わざわざ漢方薬で治す必要はないと考えています。つまり、西洋医学で手段がない空白地帯を埋めるのが漢方薬の役割です。その代表がこむら返りに効く芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)です。
現在、こむら返りがなぜ起こるのか不明ですが、芍薬甘草湯がこむら返りに効果があることは分かっています。今後、こむら返りのメカニズムが科学的に解明されて、それに合った西洋薬が登場すれば、芍薬甘草湯の出番は減るでしょう。多くの経験の積み重ねによって効果が実証されている一方で、数千年前の薬を使い続ける必要もないのです。
しかし、それまでは漢方薬を大切に使っていきましょう。漢方薬が確実に効く領域を見極めるために、私たちは臨床試験を行って科学的な証拠(エビデンス)を構築しています。漢方薬は漢方薬が得意とする領域で使いましょう。そもそも、西洋薬と漢方薬ではアプローチ方法が違うにも関わらず、西洋薬と同等の効果を期待されるのは、漢方薬にとって気の毒な話です。また、さまざまな種類の漢方薬をすべて一緒くたにして効く・効かないという議論も、漢方医療を行う側から見ると非常に苦しいことです。
今後、少しずつですが漢方薬のエビデンスが増えていき、漢方の効果的な使い方が分かってくると思います。なお、エビデンスが確立していないものは「まだ分からない」ということであり、効果がないということではありませんので、その点は勘違いしないでいただければと思います。
中医学理論や漢方医学理論を必ずしも理解する必要はない
漢方薬に興味を持って、一般向けの書籍を読んでくださる方がいらっしゃると思います。大抵の一般書には最初に中国の医学である中医学や漢方医学の理論の解説が載っています。なかでも五行説は薬膳理論のベースにもなっていますので、参照する人が多いのも事実です。五行説に限らず、古代インド医学(アーユルヴェーダ)を源流とする陰陽説や、ヨーロッパで使われていた四体液説※などは、「世の中のことはいくつかに分類でき、それで説明可能である」という共通の考え方を採用しています。
陰陽五行説は、積み重ねられてきた中国薬の使用経験をもとに作成され、まだわかっていない治療方法を発見しようとしたものです。しかし、日本では江戸時代の医家である吉益東洞が、陰陽五行説を観念的であるとして否定し、経験というエビデンスに基づく「傷寒論」を重視する考えを打ち出し、今もそれが日本漢方のベースになっています。
もちろん、現在でも、医師によっては、中医学を参照される方もあると思います。しかし、一般の方が医師の治療を受けたり、ドラッグストアで漢方薬を購入される際には、漢方の理論を理解できなくても問題ないと考えています。よくわからない、実践できないということで不安になる必要はありません。専門家に安心してまかせていただければと思います。
※四体液説(したいえきせつ):古代ギリシャ・ローマ時代における、人間の体は血液、粘液、黄疸汁、黒胆汁の4種類の体液から成り立っており、病気はこの体液の量的な釣り合いが乱れることで発症すると考える説

日本薬科大学 副学長/教授
1982~2014年株式会社ツムラ。2014年より日本薬科大学教授。2004年より日本東洋医学会 EBM委員会委員(2015年より、診療ガイドライン・タスクフォース Chair)。2018年、2021年、WHO西太平洋地区 伝統医学 テンポラリー・アドバイザー。2023年7月より現職。
著書に「漢方薬のストロング・エビデンス(じほう)」など。