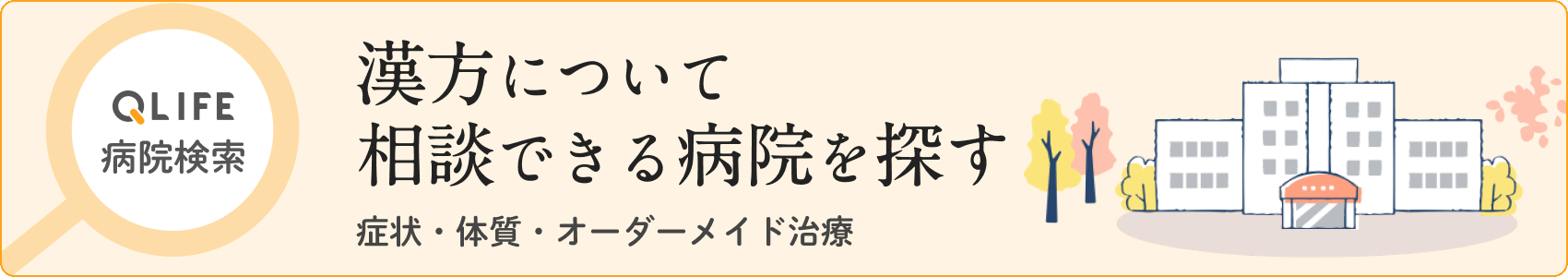【連載】Vol.3 生姜|くらしと生薬

日本のくらしに古くから根づいている生薬。たとえば、ショウガやニンジンなど、私たちの身近にあるような植物も、生薬として用いられています。薬学者であり、漢方医学の歴史にも造詣が深い帝京平成大学薬学部の鈴木達彦先生に、生薬と私たちのくらしとの結びつきについて語っていただきます。今回のテーマは生姜(しょうきょう)です。
ショウガの栽培と利用法
からだを温めたり消化を助けたりなど、ショウガは身近な薬用植物のひとつでしょう。生薬として利用されるときは生姜(しょうきょう)と読まれ、ショウガ科ショウガの地下の根茎を用います。ショウガはインドなど熱帯地域原産の植物と考えられており、日本などの温帯で栽培した場合はめったに花を咲かせませんし、越冬することも難しいとされています。秋に種子を採って、翌春に播種して殖やすという栽培法はとられず、前年収穫した根茎の一部を保存しておき、翌年に種芋として植え付けて新たな根茎を生育させ収穫しています。
ひとくちにショウガといっても新ショウガや根ショウガなど、さまざまな名称で流通しているのを見かけるでしょう。新ショウガとされるものは、種芋をもとにして新たに生育した根茎です。寿司に添えられるガリのように甘酢漬けにしたり、関東の一部の地域では谷中ショウガ、葉ショウガといって、葉がついている根茎、つまり生育したてのものに味噌などをつけて生食したりします。辛いショウガをそのまま生で食べるのかと驚く方もいるかもしれません。生育したばかりのものは特に辛みが少なく、さわやかな香りを楽しむことができます。
それでは、すりおろしたりして薬味に使っているショウガは? といわれると定義に悩むことがあります。ジャガイモも前年とれた塊茎(かいけい)を種芋として栽培しますが、生育の過程でしおれていってしまいます。一方ショウガは新しい根茎を殖やした後も植え付けた種芋は水々しい状態で残っています。新ショウガと比べて繊維質で辛みが強い種芋は、親ショウガと呼ばれています。辛みが強いので薬味として利用できますが、種芋そのままの親ショウガでは十分な供給量を確保できません。そこで、新ショウガとして収穫されたものを数か月保存しておいて辛みが増した頃に流通させたものが、今日一般に薬味に利用される根ショウガです。
図 ショウガの種類

生薬としての生姜と乾姜
生薬としてショウガを用いるときは辛みの強い古いものを用いるので、最も流通するのは数か月寝かせた根ショウガですが、親ショウガも用いることができます。以降は、これらをまとめて「ひねショウガ」と表記します(「ひね」は古いという意味を持っています)。さまざまな種類があるショウガですが、さらに収穫後の生薬としての調製法(修治法)の違いにも複雑な事情があります。
ひねショウガは中国では古くから家庭に常備されていたようで、宋代の『和剤局方(わざいきょくほう)』では、薬を調製する際に生姜や大棗(たいそう=ナツメの果実)といった常備品は除かれていて、薬を家庭に持ち帰ったあとに所定の指示に従って生姜などを合わせて煎じて服用していました。現代の中国医学や日本漢方でも古典的な立場をとるときは、生姜は薬味で用いるのと同様に生のひねショウガを用いますので、煎じ薬とするときは家庭で用意してもらうことがあります。
一方で、同じひねショウガでも生ではなく乾燥させて利用することもあります。熱を加えると、生姜の成分が変化することで辛みが増します。これは乾姜(かんきょう)という生薬として利用されています。このように、中国伝統医学は同一の植物を利用するときも調製法を工夫することで性質の異なる別の生薬として利用する術に長けています。
ただし、複雑な事情があるとあらかじめ申しましたのは、わが国で医薬品を規定する日本薬局方においてはこのあたりの定義が異なるためです。日本薬局方では生姜とは乾燥させたひねショウガで、乾姜は湯通しや蒸したりして熱を加えてから乾燥させたものを指します。加熱することによって、成分変化が促されますので、薬局方の乾姜はより辛みの強いものになります。つまり、薬局方では乾姜ではなく生姜が本来の乾姜と同じということになってしまいます。この問題は古くから指摘されていて、生姜とあった場合、薬局方の生姜を漢方処方にそのまま配合するのでは辛みが強すぎてしまうので、生の生姜より分量を少なくすることが通例となっています。また、薬局方の生姜を「乾生姜(かんしょうきょう)」として生の生姜と区別することもあります。
| 生姜 | 乾姜 | |
|---|---|---|
| 現代の中国医学や 古典的な日本漢方 |
生のひねショウガ | 乾燥させたひねショウガ |
| 日本薬局方 | 乾燥させたひねショウガ(乾生姜) | 蒸したあと乾燥させたひねショウガ |
生姜と乾姜の使い分け、古い根茎としての意味
ショウガには辛み成分のギンゲロールが含まれるほか、香りとなる精油成分のジンギベレンやカンフェン、ボルネオールなどが含まれます。ギンゲロールは加熱によってショウガオールに変化して辛みを増します。生姜や乾姜は辛みがあることでからだを温めることはよく知られていますが、漢方処方に配合される理由についてもう少し考えてみたいと思います。
生姜が配合される桂枝湯(けいしとう)や葛根湯(かっこんとう)は、かぜや感冒に用いられます。漢方では陰陽論に基づいて病気を陽病と陰病に分けており、発熱などがみられる初期段階は陽病であり、病が進行して衰弱し冷えが強くなったり、病邪が深くまで入ってきた状態を陰病とします。桂枝湯は陽病のなかでも最初期に用いられる処方で、このときの生姜は精油成分を含むことで上焦(じょうしょう=胸部)の乱れた気を整えて吐き気を抑えます。それに対して乾姜は、甘草乾姜湯(かんぞうかんきょうとう)や四逆湯(しぎゃくとう)といった陰病の処方に用いられ、陽病でも陰病にさしかかるような、進行してしまった病気に用いる処方に配合されます。調製法によって辛みを増した乾姜は、熱薬(ねつやく=からだを温める薬)として働き、からだの陽気を増すために配合されています。陽病では香りを鎮嘔(ちんおう=吐き気止め)に、陰病では辛みで熱薬にと、病気の性質の違いを生薬の調製法によって対応させています。
さらに考えさせられるのは、精油を生かして陽病の急性期に用いる一方、健胃薬の平胃散などにも配合され、慢性的な胃腸障害に対する処方にもなっている点です。熱薬として用いる陰病の処方にも、慢性的な冷え性に対して配合されることがあり、急性期と慢性期の両方に用います。慢性的な病気に用いられるのは生姜や乾姜が古い根茎であるからです。もともとの生息地の熱帯では、1年を通じて根茎は連綿と成長します。しかし、温帯で栽培するときは1年ごとに区切られて、収穫してから時間を置く、あるいは、一度掘り上げられて翌年また地中に植えられることで「古い」という性質が加わっているため、からだに長く留まった冷えや水毒を除くと考えることができます。
精油を生かして生のショウガを使うのか、辛みを生かして乾燥したショウガを使うのか。新ショウガを使うのか、数か月保存した根ショウガを使うのか、はたまた、1年間種芋として利用されたさらに古い親ショウガを使うのか。単にからだを温めるということだけではなく、鎮嘔や健胃の働き、温めるにしても長らく留まった冷えなのかどうかということもあるでしょう。ショウガひとつをとってみても、調製法や性質などを考えることで広がりを持って利用することができます。
鈴木 達彦(すずき・たつひこ)先生
帝京平成大学薬学部 准教授