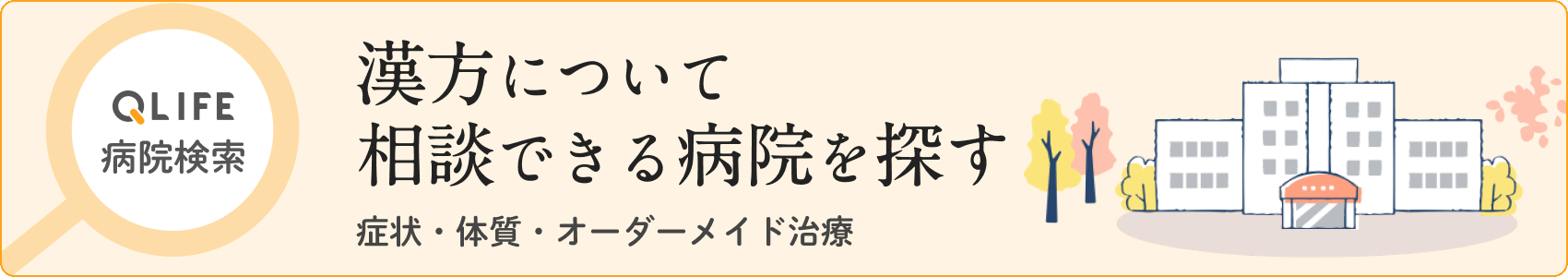【連載】Vol.2 人参|くらしと生薬

日本のくらしに古くから根づいている生薬。たとえば、ショウガやニンジンなど、私たちの身近にあるような植物も、生薬として用いられています。薬学者であり、漢方医学の歴史にも造詣が深い帝京平成大学薬学部の鈴木達彦先生に、生薬と私たちのくらしとの結びつきについて語っていただきます。今回のテーマは人参(にんじん)です。
長い年月をかけて栽培する生薬
漢方薬は通常、複数の生薬を組み合わせてできています。生薬の多くは薬用植物から、根や樹皮、根茎、果実といった特定の場所を選んで利用されているものです。今回ご紹介する人参は、代表的な生薬のひとつであり、古くから漢方薬に利用されてきました。
生薬としての人参は薬用人参や、朝鮮人参、高麗人参といわれるもので、オレンジ色をした、ふだん食用にされるものとは異なります。薬用の人参も栽培年数の若いものは天ぷらにして食べることもありますが、あまり一般的ではないでしょう。食用の人参はセリ科の植物で、畑で栽培すると早ければ3か月程度で収穫できます。それに対して薬用の人参は、ウコギ科に分類されるオタネニンジンという植物の根を採取したものです。オタネニンジンは多年草植物で、生薬として出荷されるには4〜6年程度の長い栽培期間が必要になるため、非常に高価な生薬です。栽培するときは強い日差しや雨風を嫌うため日よけを設置しなければならず、肥料をやりすぎても駄目で、長い年月をかけてじっくりと根を肥大化させるようにします。とても手間のかかる薬用植物です。古くから珍重されている生薬だけに、野生のものは取り尽くされていると考えられており、このように栽培するしかありません。
効能は医学概念の違いで変化する?
生薬の効能は? と思うとき、今日ではインターネットを利用して簡単に情報を得ることができるでしょう。人参を調べますと、滋養強壮や補気(ほき)といったように元気が出そうな効果が並べられています。からだの気を補う、補剤の代表格であると言っても過言ではありません。しかし、人参のように古くから利用されてきた生薬は、医学概念の違いによって効能について異なる解釈がされることがある、と申し上げると驚かれるでしょうか。
「傷寒論(しょうかんろん)」は漢方の主要な原典で、諸説ありますが2世紀ごろには成立したか、おおもとのものがあっただろうとされています。ここでの人参は、補剤としては考えられておらず、横隔膜、季肋部の中心に位置するみぞおちにできた塊を除くために利用されています。
「傷寒論」から1,000年ほど経ちますと、四季の移り変わりである「四時の気」が、からだにどのように影響するかという運気論による医学理論が注目されたり、漢方医学は元来食物の消化には無頓着なところがあったのですが、インドや西域の医学に影響を受けて消化に関する漢方薬が増えてきたりしました。そのような医学概念の変化によって、人参は四君子湯(しくんしとう)や六君子湯(りっくんしとう)など脾(ひ)や胃の気を助けて消化不良に用いられる漢方薬に組み込まれるようになり、広い適応を持つ補剤の補中益気湯(ほちゅうえっきとう)や十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)の中心的な生薬と考えられるようになります。
それでは、昔は人参は元気を補う生薬ではなかったの?というと、そうでもないようなのです。中国伝統医学の薬物書は「本草書」と呼ばれますが、「傷寒論」と同じくらいに書かれたとみられる本草書の記載には、人参は「魂魄(こんぱく=たましい)を定めて精気を固める」とあります。江戸時代では、危篤となったときになんとか踏みとどまらせようと庶民でも高価な人参を買い求めたといいます。人参の興奮作用を期待したということもできますが、精気がからだから抜け出さないようにするために使われていたのでしょう。大根などの根菜が人の足のような形で掘り出されることがありますが、こうしたことが人参でも起こり得ます。本来は直根の人参が枝分かれして、あたかも手足がある人のようにみえるものは人形(ひとがた)人参などと呼ばれ珍重されていました。人参に人の精気を留める「固精(こせい)」の働きを期待していたことの表れでしょう。
外界との交流を担う胃気・膏肓を活性化する
人参の効能として挙がる4つの効能、心下部(=みぞおち)の塊の除去、消化を助ける働き、脾胃の気を補う(脾胃の働きは、運搬し、消化する「運化作用」ともいわれ、消化によって得られた精気〈水穀の精微〉をからだに巡らせると考えることもあります)働き、精気の離散を留める固精、を結びつけるものは何でしょうか。キーとなるのは、「胃気(いき)」、「膏肓(こうこう)」の働きです。胃気とは、食べ物を消化する器官としての胃ではなく、胃気の脈ともいわれる、外界の気をからだに取り込む働きを意味します。
中国伝統医学よりも、もっと広く東洋思想といってもよいかもしれないことですが、人間の営みは天の気と地の気といった外界の気を取り入れて、自然の摂理に同調して生きることが理想とされます。外界には法則性があり、季節であれば四季の気を取り入れて春夏秋冬に適応させますし、1日のうちでも昼を陽、夜を陰として、陰陽に適合させて暮らすとよいということになります。上から降りてくる天の気と下から上がってくる地の気をからだに引き入れることを考えるとき、臓腑(ぞうふ=中国伝統医学でいうところの内臓)の中心にあるのが脾胃であり、この働きが胃気となります。さらに、天地の気を上下から取り入れるための上下動は呼吸によってもたらされます。坐禅を組んで腹式呼吸を行い、臍下丹田に気を集める方法はこうした姿勢と似通っています。中国伝統医学では、体幹を上焦(胸部)・中焦(上腹部)・下焦(下腹部)の3つに分けることがありますが、この時の境界となる横隔膜と臍(へそ)のラインに意味を持たせます。それぞれを膏肓といって(膏が横隔膜、肓が臍のライン)、上下動をすることで天地の気を取り入れ、大宇宙の法則性に自らのからだを合わせるのです。
人参は外界との交流を担う胃気の働きを活性化させます。胃気は膏・横隔膜の動きに関わっていますので、心下部や季肋部に集まってきてしまった病邪を除くことを助けます。膏肓の上下動は天地の気を取り入れるだけではなく、からだの中の循環をもたらします。また、中国伝統医学が次第に食物の消化を重視するようになり、外界との交流を担う胃気から消化器としての胃の役割が栄養を巡らせる脾胃の運化作用に結びつきます。自然の中で生きるとき、ひとりの人間の命など大宇宙に比べれば矮小なものです。膏肓の上下動、胃気の働きによって天地の気を常にからだに取り入れようと努めなくては、体内の精を維持することができないのです。さもなければ、人間の精はたやすく離散して天地に還ってしまうものです。人参による胃気の活性化は、根源的な精を維持することにつながります。
生薬の効能を考えるとき、これは何に効く、あれは何に効く、と手当たり次第に調べていくのでは、先々にある様々な情報に戸惑うことも多いでしょう。枝葉末節ばかりにとらわれては風に吹かれて揺らぐばかり。生薬の運用法の背景にある伝統的な生理観や治療理論を考えることで、揺らがぬ幹を見据えられないだろうかと考えています。
鈴木 達彦(すずき・たつひこ)先生
帝京平成大学薬学部 准教授