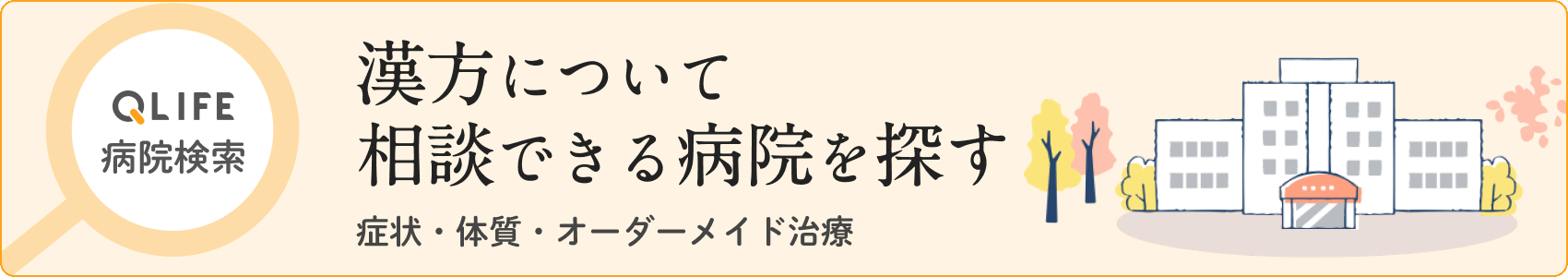高齢者と漢方 vol.3
世界でもっとも高齢化がすすんでいる日本では、高齢者の多剤併用や残薬の多さなどが課題になっています。複数の症状を抱えることが多い高齢者の薬物治療は複雑で、一筋縄では解決できません。そうした中、安価で1つの薬剤が複数の症状に効果を示すことが少なくない漢方薬の存在価値が再認識されつつあります。高齢者医療における漢方薬の位置づけについて、東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療共同研究講座 特命教授/東北大学病院 漢方内科 副診療科長の高山真先生にお話を伺いました。(村上和巳)
複数の症状をひとつの薬で改善できるのが漢方薬
――2007年から日本全国の医学部のカリキュラムに漢方教育が加わり、医療機関で漢方薬を処方する医師も増加していると聞きます。西洋薬と漢方薬の特徴、メリットとデメリットについて教えてください。

西洋薬のメリットは基本的に単一の成分で作用機序が明確、薬剤の正確な血中濃度も測定したうえで投与できることです。一方で有効性を発揮するポイントは絞られるので、複数の体の不調・症状を抱えがちな高齢者の場合、それぞれの症状に合わせて薬を投与すると、必然的に服用薬が増えてしまいます。
具体例を挙げると、高血圧症で血圧のコントロールに難渋しているケースは、降圧薬を2~3種類服用していることもまれではありません1)。そこに睡眠障害があれば睡眠導入薬、お腹の不調があれば消化器治療薬が併用され、これだけで服用薬は5種類を超えてしまいます。一般的に5種類以上の薬を服用することは多剤併用と言われ、副作用の発生頻度も高まると報告されています。
それに対し漢方薬は、1つの薬の中に複数の生薬が含まれ、個々の生薬にも複数の成分が含まれています。これらの成分が、低濃度で体内の複数のポイントに作用し、体調・症状を改善します。その意味では漢方薬は単剤でも多剤併用のような側面を持ちます。
こうしたそれぞれの特性を生かしながら、西洋薬と漢方薬を上手に併用するということが最近では一般的になっています。
例えば胃腸が弱く食事後に腹部膨満感や腹痛があり、下半身が弱くなり力が入らない、排尿に勢いがない、睡眠障害があり、認知機能も低下しつつあるなど、複数の症状がある高齢者の場合、これを西洋薬で改善しようとすれば、それぞれの症状に合わせた薬を処方することになり、相当な薬剤数になります。
これに対して漢方薬では、体を元気にする成分で体に力が入るようにし、その効果で排尿障害、消化管の働きも改善する。そのうえで若干の精神安定作用がある成分が入っているものを選ぶということになります。具体的に言えば、加齢により心身が老い衰えた状態を指す「フレイル」への効果で注目されている2)漢方薬・人参養栄湯(にんじんようえいとう)がその1つです。
前述のような複数の症状を抱える人が、すでに消化管改善薬や排尿障害治療薬、睡眠導入薬などを服用していたとします。この人に人参養栄湯が有効性を示すならば、こうした西洋薬は必要最小限まで減らすことができるわけです。
一般的に西洋薬はいわゆるハード・エンドポイントと呼ばれる、客観的な定義のある治療目標には非常に有効なことが多いのに対し、漢方薬はソフト・エンドポイントと呼ばれる、明確な定義が難しいQOL(生活の質)を改善するような症状に有効で、それぞれに合わせてうまく併用することが今後の薬物療法の肝になると考えています。
――漢方薬を取り入れることで多剤併用の問題はかなり解消されるということでしょうか?
漢方診療に従事する医師が集う日本東洋医学会などでは、近年「漢方薬のポリファーマシー(多剤併用)」の問題が指摘されています。
本来西洋薬の多剤併用解消に貢献するはずの漢方薬でなぜ多剤併用が問題になっているかというと、大きな理由は医師向けの「診療(治療)ガイドライン」の弊害です。現在では様々な病気について各医学系学会が作成した医師向けの診療(治療)ガイドラインで漢方薬の推奨に関する言及があります。
本来、漢方薬は単に症状に対して処方するものではなく、体質や生活習慣などを患者さんから詳細に伺って処方するものですが、西洋薬に慣れた医師は、ガイドラインの記述だけを見てある症状に対してはある漢方薬を、別の症状に対しては別の漢方薬をという形で、結果として西洋薬のような多剤併用を行ってしまうことがあります。これは本来の漢方薬の使い方とは異なるものです。
一例として、漢方薬の約7割には甘草という生薬が含まれていますが、漢方薬を多剤併用してしまうと、甘草の量が重複してしまう現象が起こります。場合によっては3剤くらいの漢方薬を服用することで1日の甘草の服用量が3gを超えてしまいます。この状態で長く服用し続けると、血中のカリウム濃度が低下し、血圧が上がりやすくなったり、不整脈が出る低カリウム血症を発症したりしてしまいます3)。
――漢方薬の多剤併用に関して対策はあるのでしょうか?
高齢者の場合、3種類の漢方薬を1日3回服用することは体への負担になることもあるので、朝晩の1日2回にするなどの工夫も必要です。
また、漢方医療では、独自の理論に基づいた診断のうえ処方を決めます。例えば中国の古代自然哲学の概念では2つの相対する事象を「陰陽」という言葉を使って表現します。具体例を挙げると、昼を「陽」、夜を「陰」と考えます。この考え方は漢方薬の処方にも入っています。そして漢方薬で興味深いところは、この概念に沿うと、日中つまり「陽」の時の服用で効果を示しやすい漢方薬、逆に夕・夜の「陰」の時に効果を示しやすい漢方薬というものがあります。
漢方の考え方でいう人間の生命エネルギーや体の働きを表す3つの生理的因子「気・血・水」のうち、西洋医学でいう精神的、神経的、機能的エネルギーを指す「気」に作用するものは朝や昼、気によって巡らされる赤い液体、つまり西洋医学でいう血液に相当する「血」に作用するものは夕方から夜に効果を示しやすいのです。
これを利用して気に作用しやすい漢方薬は朝昼のみ、血に作用しやすい漢方薬は夕夜のみの服用にして、全体の服用量を減らすことは可能です。そのうえで症状の改善などを見ながら、徐々に服用する種類も減らすなどの対応も検討していきます。
不安症やめまいなどは漢方薬が望ましいことも
――高齢者で漢方薬の活用が望ましい疾患領域にはどのようなものがあるでしょうか?
不眠や不安に使われるベンゾジアゼピン系抗不安薬は、依存性があることが知られています。現在高齢者で若い頃から服用し始めた方などでは服用を止められず、離脱を試みると不安感が出て眠れない状況はよくあるケースです。とりわけベンゾジアゼピン系抗不安薬の中でも短時間作用型のものは即効性がありますが、効果消失も急激に訪れます。ヒトの体はこの状況に対応しようとして疲労を感じ、その結果不安になり、再び薬に手が伸びます。結局のところ、不安の症状も含め緩やかにコントロールした方が望ましいのです。そして高齢者では筋弛緩作用や注意力減退が起こる結果、副作用であるふらつきが原因で転倒して骨折する、眠気による自動車運転時の事故、さらには認知機能の低下などの危険性もあります。
このようなケースでは加味帰脾湯(かみきひとう)、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)などを使うと、緩やかに不安の症状を改善でき、ベンゾジアゼピン系抗不安薬の減量や離脱が可能になる場合もあります。これは今お話しした精神的な症状の変動の幅を減らして、患者さん本人が薬に頼らずコントロールができる範囲に症状を改善するための処方です。
また、高齢者だけでなく若年者にもありがちな症状としてめまいがあります。特に朝に体のスイッチが入らず起きられない、起きるとめまいがするというものがあります。ベンゾジアゼピン系抗不安薬の依存性の問題が浸透した影響で、新たにこうした症状を訴える若年者に対しては、抗不安薬を控えることが浸透しつつあります。これは正しい処方のあり方である反面、選択肢が限られる難しい側面もあります。そこでめまいを改善する苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)で緩やかに体のスイッチが入るようにし、その結果、日中の活動性が改善し、結果として夜に眠れるようになる処方もあります。
――ベンゾジアゼピン系抗不安薬に限らず、最近は高齢者で睡眠導入薬が漫然と処方されていることが問題視されています。漢方薬で解決は可能でしょうか?
こうした場合は個々の患者さんがどれだけ睡眠が必要かという点から検討が始まります。そもそも眠れないこと自体が問題と考えすぎないことです。眠れないために日中の自動車運転中に眠気を感じる、日中眠くてだらだら過ごすという症状があるならば、睡眠時間が足りないという問題を抱えていると判断します。ただ、高齢者の場合は、生理現象として若い時のようにぐっすりは眠れず、睡眠時間が短くなる、睡眠そのものが浅くなることを最初に理解していただくことが何よりも重要です。そのうえで眠れない原因を探り、まずは日中の活動性を高めて夜眠れるようにする、睡眠の2時間前からスマホなどの強い光を見ないようにする、睡眠前に入浴をして一度体温を上げてから床につく、日中の眠気は10~15分の昼寝で対処するといった指導をします。それでも眠れない状態が解決できない場合に初めて漢方薬の処方を検討します。使われる漢方薬としては、不安があって眠れない場合は帰脾湯(きひとう)、心身の疲れで眠れない場合は酸棗仁湯(さんそうにんとう)、イライラ感で眠れない場合は抑肝散(よくかんさん)が代表的です。睡眠障害を漢方薬で改善しようとすることのメリットの1つは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬のような依存性がないことです。
体力の低下も漢方なら対応できることも
――高齢者では加齢により心身が老い衰えた状態を指す「フレイル」という言葉が最近よく使われます。この状態に対する漢方薬の治療について教えてください。
高齢者では全体的に老化に伴い体力が落ち、元気がなくなった状態は珍しくありませんが、西洋薬には体を元気にする薬は基本的に存在しません。しかし、漢方薬には弱った体力を回復させる「補剤」と呼ばれる薬があります。補剤の代表的なものとして補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、人参養栄湯、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)があります。
体力がなくなる、弱くなることを漢方医学の考えに沿って分類すると2種類に分けられます。
漢方医学ではヒトの内臓全体を指す概念として「五臓六腑」という言葉があります。五臓は、「肝・心・脾・肺・腎」の5つで、このうちの「腎」は西洋医学でいう泌尿器・生殖器などの臓器を指しますが、同時に腎には先天的に父母から受け継いだ生命力が宿るとされています。一方で「後天の気」という概念もあり、呼吸と食物から消化管を通じて得られる「気」、いわばエネルギーを指します。
この考え方に沿って高齢で体が弱る現象を、持って生まれた腎のエネルギーが徐々に失われていく「腎虚(じんきょ)」と定義します。症状としては筋肉や骨が衰える、認知機能が低下するなどが代表的なものです。この場合、腎のエネルギーを下がりにくくする、あるいは少し補う漢方薬として牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)、八味地黄丸(はちみじおうがん)、六味丸(ろくみがん)が使われます。一般的には、下半身の冷えがある人には八味地黄丸、手足がほてる人には六味丸が適しています。
後天の気に関しては、消化管が弱ければ食物からのエネルギーが吸収できず、元気がなくなり、さらに体を構成することができないので痩せてしまいます。最近、よく言われる「フレイル」は先天の気の衰えに後天の気の衰えが加わった形が多いです。
この状態を進ませないためには、しっかりと食事をとることをサポートする必要があります。この点でよく使われる漢方薬が六君子湯(りっくんしとう)です。最近の研究では、六君子湯は摂食亢進ホルモンであるグレリンの分泌を促進することが明らかになっています4)。
また、食事をとることへのサポートとしては、お腹が冷えて食べられない人には消化管を温めて温めて食欲を上げる人参湯(にんじんとう)、手術後でお腹が冷え痛くなりがちで食事がとりにくい人には大建中湯(だいけんちゅうとう)という選択肢もあります。
さらにフレイルの状態でもお腹も下半身も弱い場合は六君子湯と八味地黄丸の併用、食事もとりにくく、肺機能が落ちて気が入りにくい場合は補中益気湯、これに腎虚があるならば八味地黄丸を併用する処方も昔から行われ、フレイルには相性がいいと考えられます。
そしてこれらのような処方の良いとこ取りをして服用しやすくしているのが人参養栄湯、十全大補湯です。いずれも体を温めて気を上げる作用があります。ただ、人によってはこの2剤ですら、服用時に胃もたれを起こすことがあります。その場合は内服方法を食後にしたり、1日内服の総量を減じるなどの工夫で対応することが多いです。
補剤で体調が回復してから運動をするよう心がけると、さらに症状の改善が期待できます。
- 参考
-
- 西村誠一郎ほか. 血圧 2018: 25(5); 364-37
- 乾明夫. 心身医 2017: 57(10); 995-996
- 医薬情報委員会 プレアボイド報告評価小委員会. 日薬病誌 2007: 43(9); 1171-1173
- 武田宏司ほか. 日消誌 2010; 107(10); 1586-1591
東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療共同研究講座 特命教授/東北大学病院 漢方内科 副診療科長
2011年東北大学病院 漢方内科 副診療科長。2013年現在東北大学病院 総合地域医療教育支援部准教授。2019年から東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療共同研究講座 特命教授